女神の乳房 第2話

夫を送り出した後、長い髪をしばり、いつものように掃除と洗濯を済ませた。
四LDKのマンションは夫婦二人だけなので、それほど汚れることもないのだが、毎日時間を費やして部屋のすみずみまで掃除機をかける。夫が細かい性格だというわけではなく、裕美子の性分だった。
二十帖のリビング、パソコンなどを置いて夫が書斎としている部屋、裕美子の衣装部屋兼書斎、そして夫婦の寝室に、残りの一部屋は物置として使っている。
床面積が120㎡はある大型のマンション。裕美子との新居として夫が購入したのだが、分譲業者が取引先だったので少し安く買えたのだ。築八年経つが、住み心地は抜群で裕美子はとても気に入っていた。ただ高級マンションなので、住人も大企業の役員や上級の公務員等が多く、人付き合いがあまり得意でない裕美子にとって、取るに足らないものではあるが、それだけが悩みだった。
最上階の部屋は風もかなり強い。洗濯物を干し終えると、裕美子は自分のために紅茶を入れた。ソファーに深く腰掛け、物思いにふけりながらゆっくりと飲む。
中堅の不動産会社を経営している夫は、この不況の中も着実に業績を伸ばしている。現在の何不自由のない豊かな生活も、すべて夫のおかげだと思うと、できる限り尽くしていきたい。
(夫婦の営みがないことぐらい、何でもないわ。こんなに幸せなんだもの)
忙しく身体を動かしている間はそう思うことができるのだが、日が暮れ、月明かりに照らされる部屋に独りでいる時には、また昨夜のような想像をしてしまう。肯定と否定、毎日がその繰り返しだった。
二十六歳で結婚して八年、子供はいないが夫婦仲は円満だ。二十三歳のころに結婚を考えていた相手がいたが、ある事情で裕美子の方から泣く泣く別れを告げた。夫にも、誰にも話したことのない、自分の心の中だけに留めてある思い出したくない深い傷だ。
唐突な電話の音に、裕美子の思索は中断された。
「はい、小笠原でございます」
いつものように、少し声を高くして受話器を取った……。
![]()


「あっ、裕美子さん。貴彦です」
元気の良い声は、夫の連れ子の貴彦だ。
再婚だった夫には息子が一人がいた。離婚直後は前妻と暮らしていたのだが、病弱だった前妻の死後、十九歳になっていた一人息子を夫が引き取ったのだ。裕美子に気を使っているのか、大学入学時から二十七歳になる現在まで、夫婦のマンションの近くに部屋を借りて独り暮らしをしている。彼は裕美子のことを「お義母さん」ではなく、あえて「裕美子さん」と呼ぶ。別に不仲なのではなく、彼なりの親しみの表現なのだ、と裕美子は思っている。
「どうしたの、こんな時間に? 会社は?」
「うん、ちょっと今日は休みをもらったんだ」
車好きの貴彦は自動車のディーラーに勤めている。今日は日曜日なのでかきいれ時のはずだった。同じく客商売の夫も日曜出勤はあたり前なのでその辺は心得ている。
「実は……、裕美子さんに相談があるんだけど、そっちへ行っていいかな?」
冗談のひとつも飛ばしてくると思ったのだが、意外に深刻そうだ。
「どうせ洗濯物やなんかたまってるんでしょう? もう少し後で良かったらわたしがアパートに行くけど」
違和感を覚えた裕美子は、あえて軽く切り返した。
「悪いけどお願いできるかな、裕美子さんにしかできない相談なんだ」
「そう、わかったわ。じゃあ一時間後に」
浩一郎が切るのを待って、裕美子は受話器を置いた。
(わたしにしかできない相談? 女性のことかしら?)
いろいろと思い巡らしながら、初めて貴彦に会った時のことを思い出した。
(あれは貴彦さんが高校を卒業した直後だったわ)
知人の紹介で知り合った夫との交際期間は約一年だった。年齢的な包容力に加え、経済力もあった夫との年齢差はほとんど気にならなかった。裕美子にはすでに両親は亡く、口うるさい親類もいなかった。時の流れに心の傷も癒えかかっていた時だったので、プロポーズをすぐに受け入れたのだ。ただ浩一郎が大学受験を控えていたので、実際に入籍して彼に紹介されたのは合格が決まってからだった。裕美子が自己紹介した時の貴彦の驚いたような表情が印象に残っている。
(あんまり若くいなお母さんでびっくりしたんじゃないかしら)
手早くティーカップを片付け、黒いワンピースに着替えた。肌の白さが引き立つ黒い服が裕美子の好みだ。いくら義理の息子とはいえ、女として最低の身支度は整えなければならない。軽く化粧をすると、鏡の前に立って自分の姿を確認した。
(うん、合格、合格。でも少しお化粧が濃すぎないかしら?)
軽くしたつもりが、思いのほか濃くなっていたらしい。
(いやだわ、わたし。誰のためにお化粧してるの? 義理とはいえ息子に会いに行くのよ。もしかして最近見る夢のせい?)
鏡の中の自分に語り掛ける。
貴彦のアパートまでは裕美子のマンションから歩いて五分の所にある。わずかな時間だが、冷たい風に頬を叩かれた。
(マフラーでも巻いてくれば良かったわ)
風の音がいっそう寒さを感じさせる。枯葉が舞い、乾いた音で鳴いた。コートの襟を立てた裕美子の視界に、塗装の剥げかかったアパートが目に入った。
ドアの前に立ってチャイムを押すと、入ってきてよ、と貴彦の声が聞こえた。玄関ドアをあけると四帖ほどの台所、奥に八帖の洋室がある一DK。大学入学当時からなので、十年近く住んでいることになる。
「ああ、寒かった」
コートを脱いでストーブに手をかざす。室内は少し熱いくらいで、彼は半袖姿だった。
裕美子の予想に反して部屋はきちんと片付けてあり、洗濯物も溜まっていないようだ。何度かここに来たことはあるが、いつもかなり散らかっていて、掃除や洗濯もしたことがあるのだ。
(案外きれいにしてるのね、やっぱり女の人が出入りしてるのかしら?)
大型のテレビと洋酒を置いたサイドボード、ソファーが一つに趣味の歴史の本が入った書棚。家具が少ないので、部屋が広く感じられる。
裕美子から受け取ったコートをハンガーに掛け、貴彦は二人掛けのソファーを勧めた。冷たいものしかないけど、と言って冷蔵庫から缶ジュースを出して裕美子の前に置いた。
「どうしたの相談だなんて」
スカートから伸びた膝の上にバッグをのせてハンカチを取り出した。貴彦はガラステーブルをはさんで裕美子の前に座布団を敷いて座った。
「実はさ…、女性の事なんだけど……」
坊主頭に近い短髪を掻きながら、照れくさそうに言う。
「女性のこと?」
裕美子は微笑んだ。
「半年ぐらい前から付き合ってる人なんだけどね……」
缶ジュースに口をつける。何か含んだところがあるのか、言葉の歯切れが悪い。
「その女性がどうかしたの?」
義母といっても、それほど歳が離れていないので、裕美子としては姉のような気持ちでいた。貴彦はその先をなかなか話そうとしない。
(まさか問題のある人? 外国の人とか他人の奥さんとか……)
煮え切らない彼の態度に、ふとそんな思いが浮かんだ。
「結婚したいと思ってるんだ……」
煙草をくわえて火をつける。吐き出した煙をぼんやりと目で追いながら、貴彦は続けた。
「僕より三つ年上だからちょうど三十かな。三年前にご主人を事故で亡くしてね、今はお母さんと住んでるんだ。事務機器販売の会社で働いててね、最初はうちの営業所にお客さんとして来たんだ。それが半年ぐらい前かな」
栗谷美登里という名前のその女性は、社用車の購入のために営業所を訪れ、たまたま担当についたのが貴彦だったのだ。
決算期をひかえていたので、いつも以上に熱心な営業になった。その後、彼も商談で何度か彼女の会社へ行き、美登里とも親しく話すようになる。結局、彼女の会社には四台ほど購入してもらい、それでどうにかノルマを達成することができたといういきさつがあったようだ。
会った当初から美登里のことが気になっていた貴彦は、ノルマを達成できたお礼という口実で彼女を食事に誘い、そこから交際に発展したという。
美登里は背が高く、ショートカットを栗色に染め、いつも身体にぴったりとしたスーツを身につけているらしく、裕美子は自分と正反対のキビキビとした女性を想像した。
「それでわたしに何をして欲しいの?」
青いマニキュアの指でハンカチをつかみ、額や襟足をぬぐう。アップにした黒髪に白いうなじがよく映えている。
「親父にさ……、親父に話して欲しいんだ」
父親譲りの長い睫毛で上目使いに裕美子を見る。ふとした仕草が良く似ていて、やはり親子なんだと実感させることがあった。
「結婚したいってことを?」
申し訳なさそうに彼はうなずいた。煙草を揉み消し、正座に直る。
「裕美子さんにしか頼めないんだ。僕が言うよりもまずは裕美子さんから言ってもらったほうが良いと思うんだ……。だから、お願いします」
「ちょっと、ちょっと待って」
手をついて頭を下げる貴彦を制し、
「できることなら力になってあげたいけど……。わたし、その美登里さんには会ったこともないし、どんな人かも知らないわ。何をどうやって話せばいいのかしら」
戸惑いながら応える裕美子に彼は、
「もちろん、彼女には会ってもらうよ。それで裕美子さんの感じたままを親父に言ってもらってかまわないよ。裕美子さんも絶対気に入るから」
自信をもって熱っぽく語る貴彦を前に、裕美子は美登里というまだ見ぬ女性に軽い嫉妬を覚えた。
「わかったわ。将来の義母としてじっくり吟味させてもらうから」
微笑を投げかけ、ジュースに手を伸ばした。スカートの中の足をゆっくりと組み替える。
「ありがとうございます! じゃあさっそく電話するよ!」
「えっ、もしかして今から?」
「うん、善は急げって言うでしょ。彼女にも伝えてあるんだ」
貴彦は喜び勇んで携帯電話をつかんだ。
(もう、人の都合も聞かないで……。まあいいわ、バッチリ化粧もしてきたし、どうせ暇だしね)
呆れた表情の裕美子を尻目に、彼は電話の相手と嬉しそうに話している。
「近くに居るらしいんだけど、ここに来てもらってもいいかな?」
送信口を押さえて、裕美子に問う。しょうがないわね、といった感じで頷いた。
「三十分ぐらいで来れるって。裕美子さん、時間はいい?」
電話を切った貴彦は、しゃあしゃあとした表情で尋ねた。
「貴彦さん、順番が逆じゃないの?」
わざと怒ったそぶりを見せた。
↑ご精読ありがとうございます。ご満足いただけましたら、クリックをお願い致します。![]()
↑さらにご満足いただけた場合は、こちらにもお願いします。
↑こちらにもいただけると、大変ありがたいです。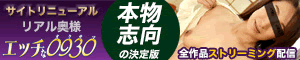

女神の乳房 | Comment(0) | Trackback(0) | Top ▲






コメント
コメントの投稿
トラックバック
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)